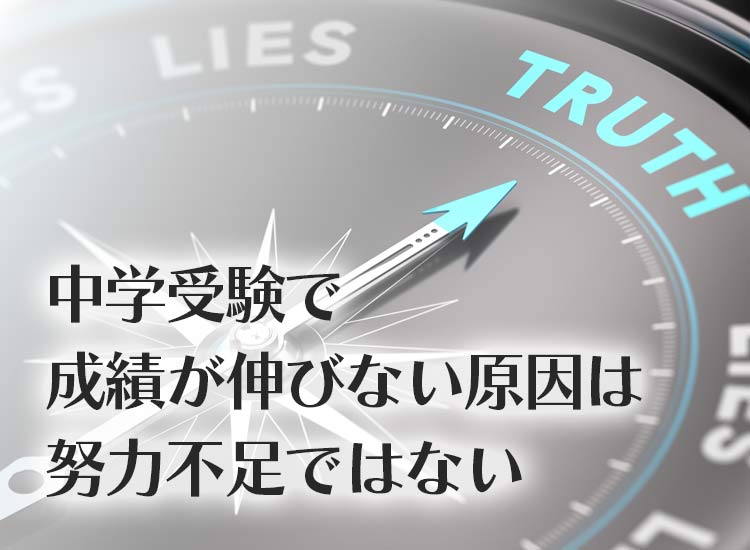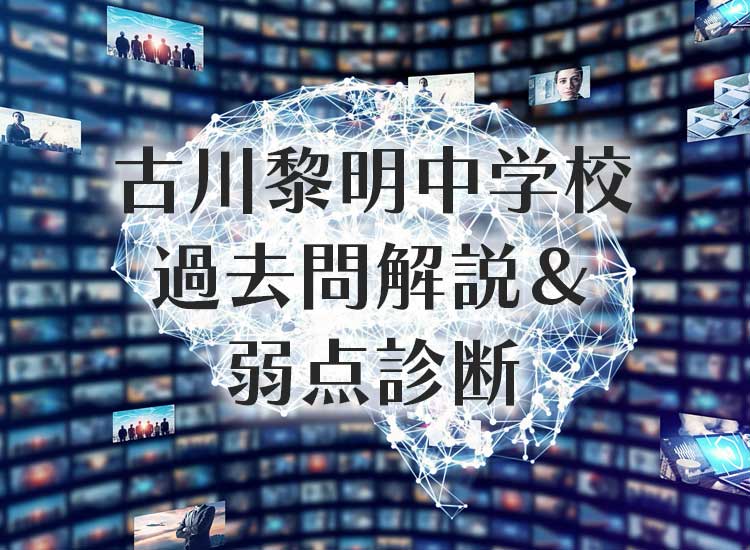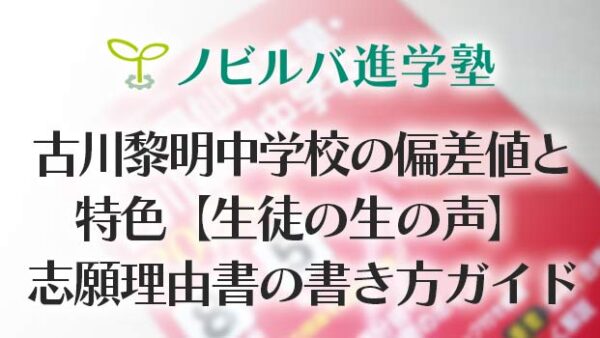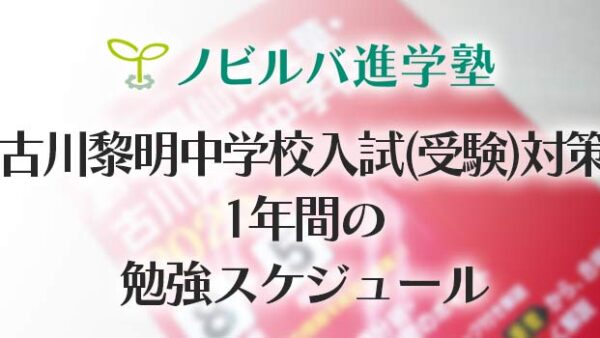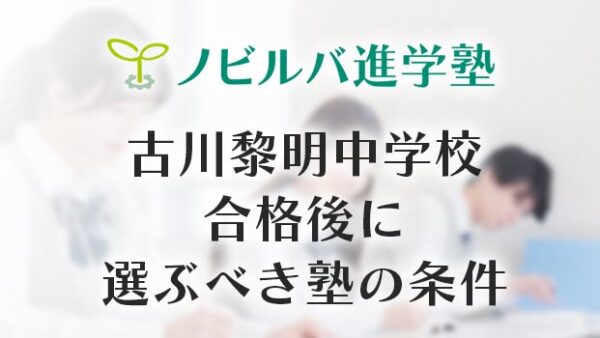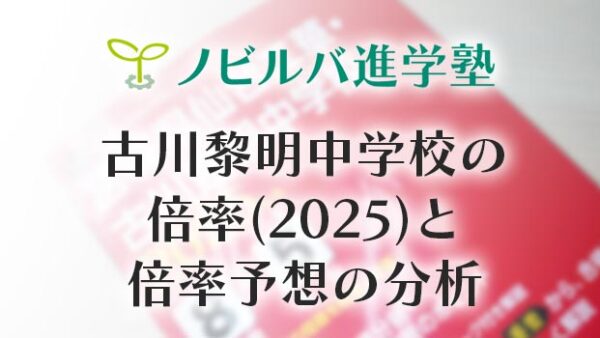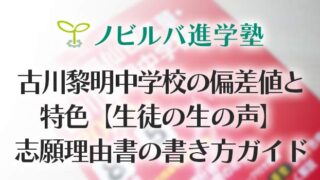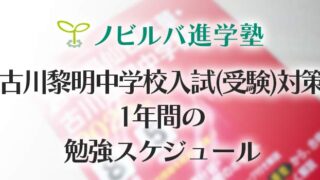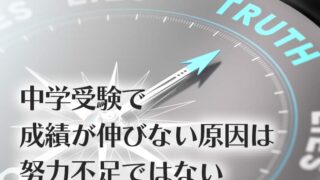入試問題と模試の傾向変化
これは小学ぜんけん模試、古川黎明中学校の入試問題共に言えることですが、文字数がかなり多くなりました。
双方2024年度から問題の傾向が変わっています。簡単に言うと「文字数で混乱させる作り」になっています。入試問題は4~5年に一度問題の傾向が変わるのですが、今年が丁度その年でした。
受験生の反応と作文の難易度
去年の古川黎明中学校を受験した生徒にも見てもらいましたが、「小学ぜんけん模試ってこんなに文字多かったけ…」「今年の黎明中学校の入試問題文字が多いな…もっと余白なかったけ…」という反応でした。
そして、作文に条件が追加されました。これは2014年~2019年の仙台二華中学校の入試で出題された傾向になり、難易度がアップしました。
今までは、作文を具体例を踏まえて、きれいに書ければなんとか点数は取れていました。しかし、今後はきれいに書けるようになった後に、「条件に従って書く」もしくは「条件に従って書き換える」ことが必要になります。これは、作文に今までよりも多くの時間を割く必要が出てきています。
試験内容の変化と対策
古川黎明中学校の入試問題は2019年度までは数学的志向が重視され、回りくどい表現をどう読み解くかに重きが置かれました。2022年度からは英語のリスニング(10分)が入り、実質問題を解く時間が60分から50分と少なくなったため、問題の難易度はいったん下がり、算数、理科、社会がバランス良く出題されるようになりました。そして2025年度からは文字数が増え、国語力や読解力、図表を読み取る力が重視される内容に変わりました。
適性検査(教科融合問題)の難しさ
適性検査問題は教科をまたぐ教科融合型問題です。読み方を工夫しないと中3でも問題を読み解けず、結構苦戦します。
実際に、古川黎明中学校の受験問題を解かせた(正しく読み解けているか確認した)際は、オーバーヒートしている生徒が多かったです。
こうなる理由は4~5教科すべての知識を同時に引き出さなければならず、得意・不得意も含まれるため脳のキャパオーバーになるからです。
文字数が増えるとなると更に大変です。国語力、読解力が低い生徒は文字数に惑わされミスが発生しやすくなります。
塾選びのポイント
今後は、読解力を着実に上げてくれる塾を選ぶべきだと思います。やんわりと書きますが塾で国語をうまく指導できる講師は少ないです(私のイメージだと室長クラス以上の講師)。大学生バイトの講師は指導しやすい数学か英語を教えていることが多いのもその為です。したがって、ここは吟味した方がいいポイントになります。(英語、算数、理科、社会は、やればやった分点数が上りやすい科目です。国語は要素がいろいろ絡むため、一般的に時間をかけたからと言って必ずしも点数が上っていくわけではありません。)
当塾の要約メソッド
当塾の国語は主に「要約力」に力を入れています。これは、模試で90点以上の点数を取っていた生徒の生い立ちを分析し、脳のどの領域を刺激すればいいか体系化したメソッドになります。数か月で読むスピードは2~3倍になっています。2倍はすぐにいきます。メソッド習得後は黎明中入試の過去問も時間が余る生徒が多いです。
ただ、このメソッドはいつも使わない脳の神経を使うため結構疲れます。その為、塾にはいつも生徒が糖分を補給できるように何かしらは常備しています(苦笑)。次第に脳は慣れるため、糖分は補給せずとも良くなるのですが、生徒はいつも奮闘しています。
古川黎明中学校の受験を検討している方は、是非参考にしていただけたらと思います。