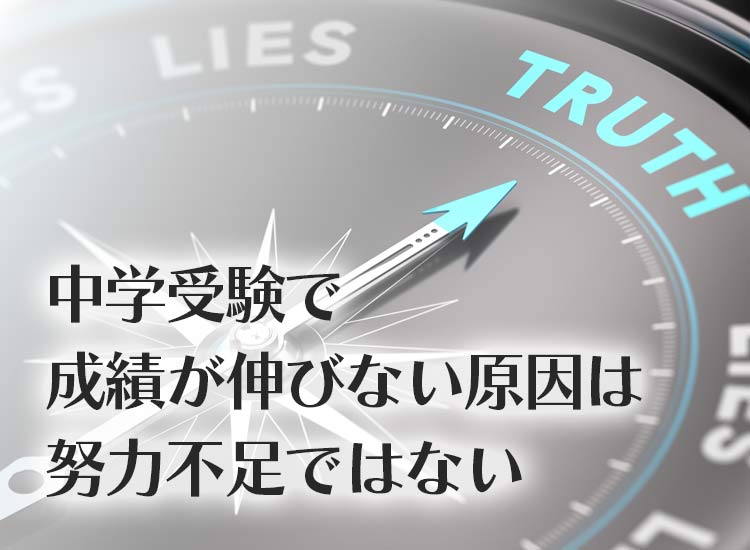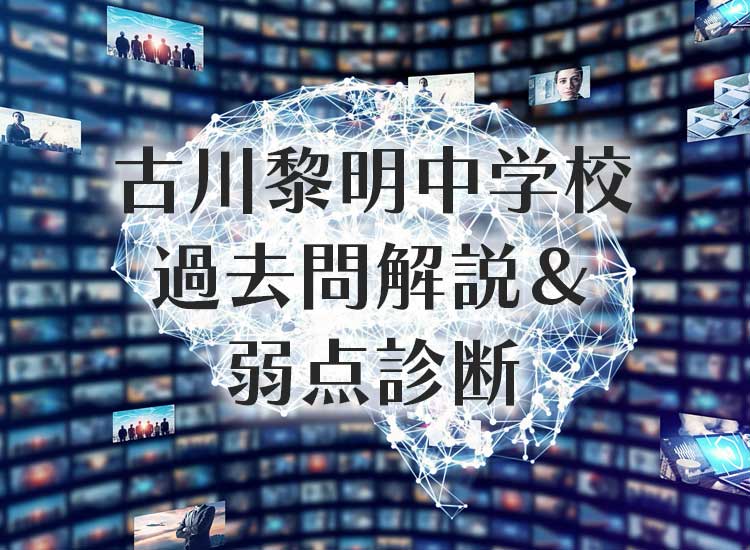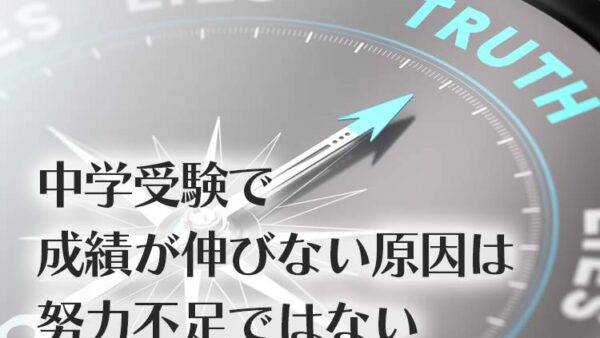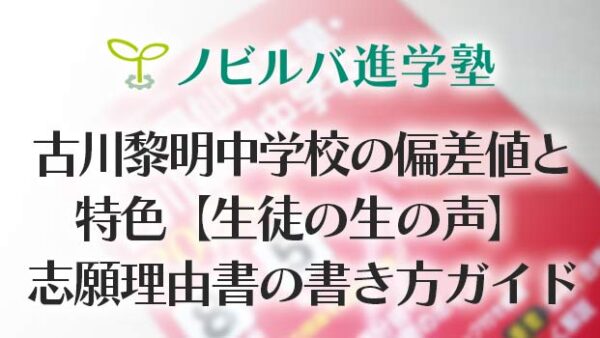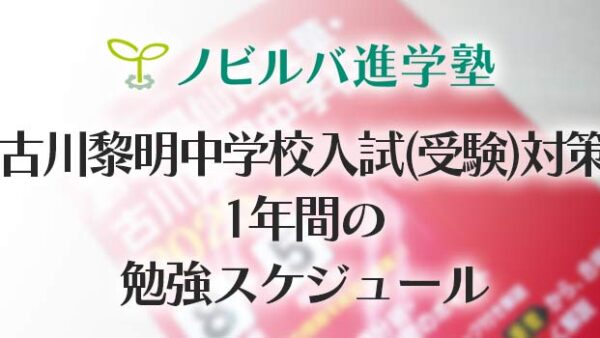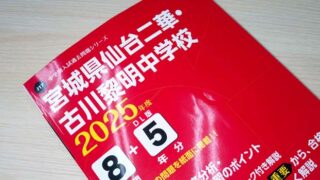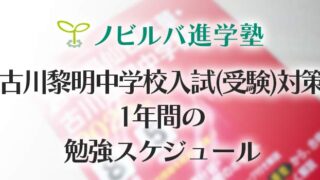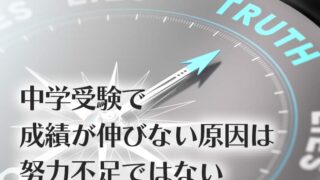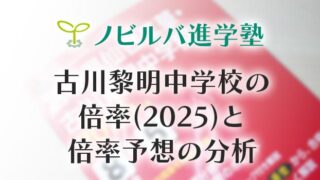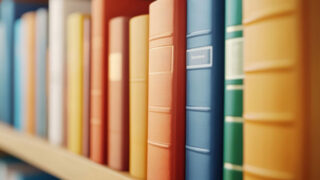英語学習の変化と課題
英語は2020年4月から小学校で必修化になりました。具体的には何が変わったかというと覚えなければいけない単語数が増えました。
小学校必修化以前は中学で1200単語、高校で1800単語の計3000単語の履修でした。必修化以降は小学校で700単語、中学校で1800単語、高校で2500単語の計5000単語になっています。
ただ、英単語は発信語彙と受動語彙に分かれており、それぞれ約半分の割合になっています。
| 発信語彙 | 意味がわかり、話したり、書いたりできるもの。 |
| 受動語彙 | 意味が分かればいいもの。話したり、書いたりできなくてもいい。 |
では受動語彙は覚えなくていいかというとそうでもなく、小学校で受動語彙だったものは中学校で発信語彙になり、中学校で受動語彙だったものは高校では発信語彙になります。その為、覚えていた方が次のステージに上がった際に学習の負担は軽減することが出来る為、少しでも知識として頭に入れていた方がいいです。
大学共通テストでも英単語が6000単語ほど出題されており、単語力はますます求められています。
中高一貫校における英単語学習
中高一貫校の英単語数は1800語、公立中学の英単語数は1200語の教科書を使っており、中高一貫校は1.5倍の量を覚えなければなりません。
では、ここで時間を増やせばいいのかというというと、それはあまりお勧めしません。他の科目でも課題が多いため現実的な選択肢としては難しいと思います。
効率的な英単語学習法
英語を効率よく覚えるにはどうすればいいのか。
結論は「なるべく書かない。発音をしてスペルも意味も覚える」です。
書くという作業は結構時間を取られる為、出来るだけ書かずに覚えた方が学習効率が上がります。
そして、発音ベースで学習するということは正しく音を聞き取れるということにもつながります。
発音とリスニングの関係
基本的に人は理解していないものは説明(発信)することはできません。「食べたことのないフルーツの味を明確に表現してほしい」と言われてもできないことと一緒です。
音を正しく発音できれば、子音と母音を細かく区別できるためリスニング力も向上します。逆に正しく発音できなければ、判別する能力が落ちるためリスニング力も低下するということです。そして、聞き取れない音は雑音としてカットされるため学習効率は低下してしまいます。
その為、いかに正しく発音し、出来るだけ書かずに覚えるかが重要になります。
当塾の英語学習法
当塾では英語は発音記号から指導しています。一見スタートが遅く見えますが、発音が正しく出来るようになれば自然とリスニング力が上り、聞き取る英語の情報量が増え学習効率が高くなります。
また、発音しながら英単語を覚えるメソッドとも組み合わせる為、書いて覚える時間が最小限になり更に学習効率が上がります。
英語の学習は様々なアプリがありますが、やはり初めは発音記号からと思っています。そうすれば、高校でよく発生するリスニングが苦手になる現象もおのずと回避できると考えています。
発音記号から練習をしなければ、発音アプリで高得点を取ることは難しく勉強のモチベーション的にはマイナスになります。※日本語の発音と英語の発音は、発音記号的にはほぼ違うと思った方がいいです。
英語の学習効率を上げるには「正しく発音し、正しく聞き取り、出来るだけ書かないで覚える」これに尽きます。
もし英語が苦手なお子様をもつ保護者様がいましたら、ぜひ参考にしていただければと思います。