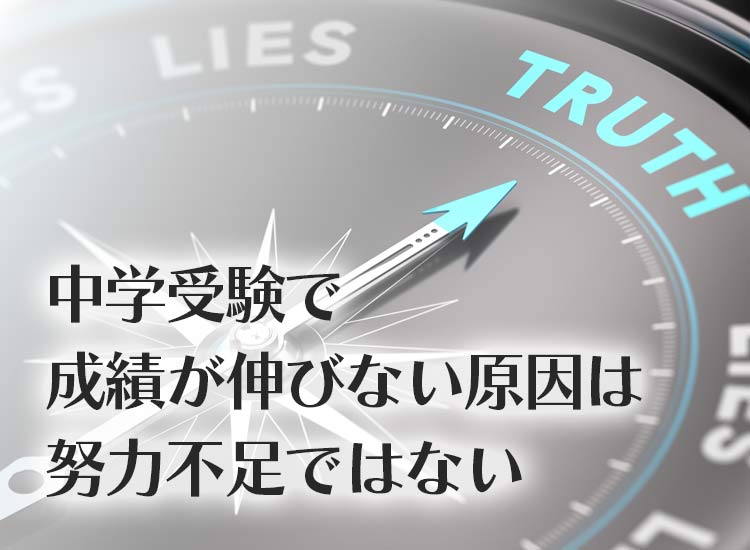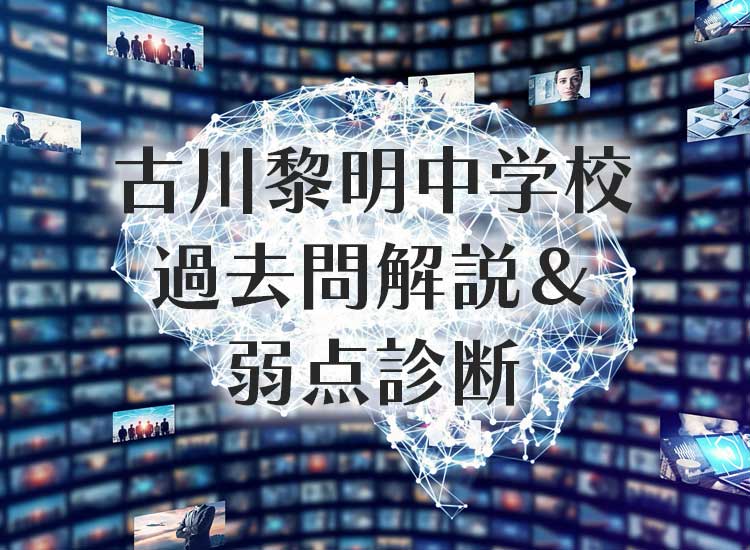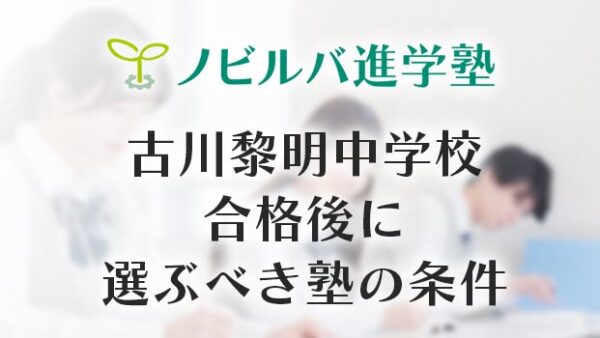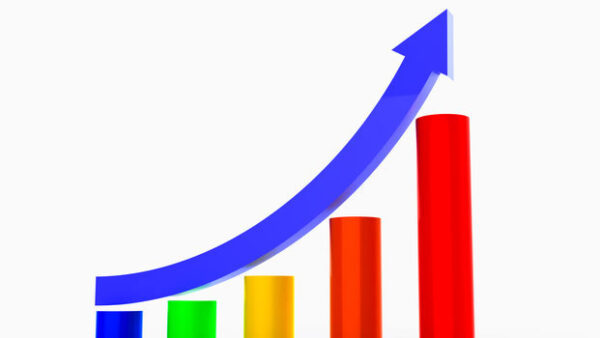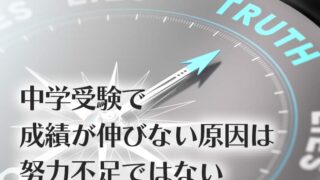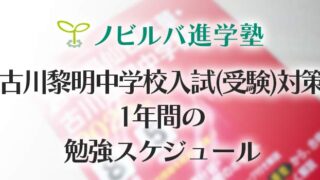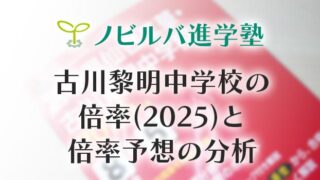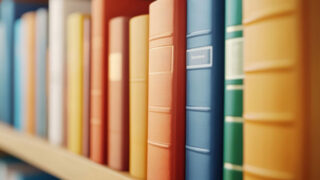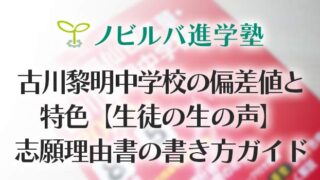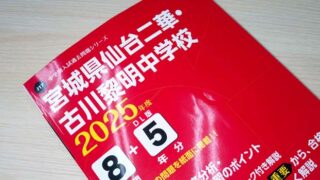記憶力と読解力は反比例の関係にある
私は記憶力と読解力は反比例の関係性にあると考えています。また、片方が大きく伸びた後はもう片方は大変伸ばしにくくなるとも思っています。
あえて利き腕とは逆の手で文字を書かないのと同じで、脳機能的に大変だからです。片方が発達した後は発達した脳機能でどうにかできないかと試行錯誤する方が簡単だからです。
その結果、得意な部分だけが伸びてしまい、どんどん差が開いていきます。
記憶力と読解力の定義
まず、それぞれをまとめると下記のようになります。
| 記憶力 | 物事を覚える力や過去の体験を忘れずに覚えている能力 |
| 読解力(以下、要約または要約力と記載) | 文章を読んでその内容を理解し要点をとらえる能力 |
反比例の関係となる理由
なぜこれらが反比例の関係になるのか。
例えば、記憶力の優れた子供がいたとします。この子にとって小学校低中学年の国語問題は簡単だとします。この場合、国語は要約する必要はないんです。全て覚えてしまえば事足ります。その結果、記憶力が成長し、要約力は育ちにくくなります。
逆に、記憶が苦手な子供がいたとします。この子も国語で同じレベルのアウトプットをしたとします。この場合、文章をそのまま記憶するには情報量が多すぎることになります。それでも、何とか処理する為には情報を圧縮しなければならず、要約が必要になります。要約力ばかりが成長すると、要約を行わない暗記物は苦手意識が芽生え育ちにくくなります。
「覚えられないから要約する(読解力)」「覚えられれば要約しない(記憶力)」
ということです。
脳の領域と発達
こうなると、根本から脳の領域が違うと考えています。その為、苦手な方を伸ばすのは大変というわけです。
両方秀でていればいいのですが、それは少数と考えています(天才タイプ)。根本から苦手な方を発達させられなければ、得意な方で疑似的に能力を再現することになります。
大半の場合は本来よりも能力は落ちるし効率も悪いという状態になります。
受験までの間に疑似的な能力で点数を取れればいいですが、一般的にそこまで行きつかない生徒もそれなりにいるのが現状です。
当塾の指導方針
当塾では、得意な能力とは別に発達が必要な場合は、根本的に能力を伸ばしていきます。
その為、結構疲れます。疲労回復のための糖分はいつも教室に常備しています。慣れない神経を使った場合は、1時間保つ体力も10分、15分で空っぽになる場合もあります。そういう時は10分ほど仮眠を取ってもらいます。その方が効果的だからです。
根本的に能力を伸ばすことを続けていると、生徒も「発達する感覚」が分かってきます。大変だけれども短期間でできるようになる為、生徒にはいつも「登山の最短コース」と伝えています。
能力を劇的に根本的に伸ばすには条件を整える必要があります。そして、根本から能力が育ってしまえば、日常生活でも容易に伸ばしやすくなります。
両方ともバランス良く伸びた稀な人を「天才タイプ」と呼んでいます。この人たちは日常生活で能力を伸ばせる為、一般的にそこまで勉強はしないようです…
もし、お子様の記憶力もしくは読解力のどちらかが伸び悩んでいる保護者様がいましたら、ぜひ参考にしていただければと思います。